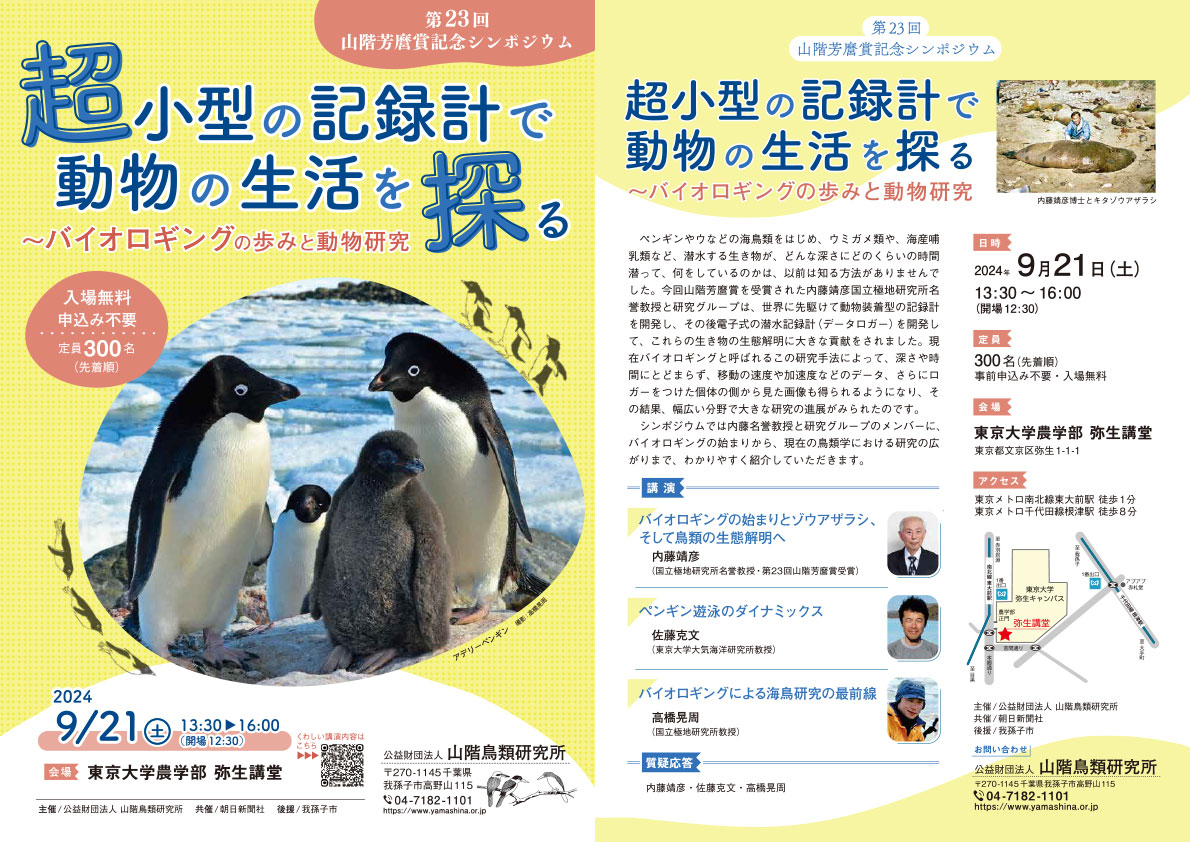第23回 山階芳麿賞 記念シンポジウム
「超小型の記録計で動物の生活を探る
〜バイオロギングの歩みと動物研究」
2024年9月21日(土)
【主催】(公財)山階鳥類研究所 【共催】朝日新聞社 【後援】我孫子市
2025年1月21日掲載
2024年9月21日、東京大学弥生講堂で第23回山階芳麿賞記念シンポジウム「超小型の記録計で動物の生活を探る〜バイオロギングの歩みと動物研究」を開催しました。受賞者の内藤靖彦 国立極地研究所名誉教授に続き、佐藤克文 東京大学大気海洋研究所教授、高橋晃周 国立極地研究所教授による講演と質疑応答が行われました。講演と質疑応答の内容を紹介します。
「バイオロギングの始まりとゾウアザラシ、そして鳥類の生態解明へ」

国立極地研究所名誉教授 内藤靖彦
今日の話題として、「海の中の動物たちは何をしている?」を振り返ってみればということで、バイオロギングの発想と背景を中心に潜水記録計による動物行動研究のブレークスルーを目指した1980年代のころと、デジタル化によるバイオロギングの普及を目指した1990年代のころの話をいたします。最後に研究が進んだゾウアザラシについても紹介します。
最初に取り組んだ1980年代はすでにアメリカを中心に動物はなぜ長く潜ることができるのかを生理学的視点から研究が活発に進められ、われわれの出る幕はありませんでした。しかし、動物はただ潜るのではなく、いかに限られた潜水時間で餌をとれるのかについての生態学的視点からの研究は進んでいませんでした。課題は潜水記録計にありました。
ペンギンにも装着可能な超小型の潜水記録計の開発がわれわれの課題でした。試行錯誤の結果、半導体のシリコンウエハーに細密線を描く技術を利用し(針角度70度のダイヤモンド針)、また記録紙としては昔の黒いごみ袋が薄くて腰があり針によるひきつれを起こさないこと、これらを使うとなんと1mm幅に100本の細密線を描けることがわかりました。この技術をあるメーカーで組み立ててもらったのが世界最小のアナログ式潜水記録計です。1984年のことです。
これを持ってやっと南極に行けるかと思ったら、隊員枠の制約から3年待たされましたが、とにかくこれを昭和基地のアデリーペンギンに着け世界で初めて小型ペンギンの潜水記録がとれました。当時としては画期的な2週間という連続記録でした。この結果、昭和基地周辺のアデリーペンギンの採餌深度は浅く(20m未満)、時間帯は15〜22時であることがわかりました。
超小型記録計ができたということが、なぜか世界中に知れ渡りました。イギリスの有名なクロクソール先生からイギリスのバードアイランドで共同研究しようと声がかかり、そこでアオメウに装着したところ、体重2.5kgのこの鳥が水深115m、5分以上も潜ることがわかり、これも世界で大きな話題となりました。
このアナログ式潜水記録計から、動物の潜り方には決まったパターンがあることがわかってきました。潜水を始めると何回も繰り返し潜水すること、潜水時間が一定していること、潜降率、浮上率も一定していること、必ず一定深度にある程度の時間とどまることがわかってきました。この行動パターンが非常に機械的なことから、潜水の理論モデルの研究が世界中でおおいに進められたのも1980年代です。
ところが問題は、「動物は潜水底部で何をしているか?」です。上下に動くジグザグ行動は何を意味するかが不明のままです。
話は前後しますが、最初のアナログ記録計ができたころ、カリフォルニア大学のル・ブーフ先生から「おまえの記録計でキタゾウアザラシの潜水行動の研究を一緒にやろう」と誘われました。当時、彼らの記録計は2週間しかデータがとれていなかったので、その先を知るためにわれわれの潜水記録計(125日連続記録が可能)を使うことになりました。最初の実験でこのアザラシは72日間で2700回の潜水を休まず行うこと、潜水時間は20〜22分で平均深度400〜650m(最大1200m、70分)であることがわかり、これは何事だということで、この動物でも潜水底部で何をしているか、なぜそんな深くに潜るのか、なぜ休むことなく連続潜水を繰り返すのかが課題となりました。
まずは、潜水底部の問題、すなわちそこで餌を食べたのかどうかを知る必要があります。このためわれわれはアナログ式胃内温度計を開発しました。これは体内と餌の温度差から餌を食べたタイミングと食べた量がわかると考えたからです。しかし、オーストラリアのアオメウでテストしたところ何回かの潜水時に採餌データはとれましたが、長期の記録は困難でした。この方法は世界中の研究者がトライしましたが、結局吐き戻しや感度の問題からほとんどうまくいきませんでした。
さて、1990年代に入るとデジタル技術が普及し始めました。われわれもデジタル記録計を作ろうということになりました。細かい経過は省略しますが、多くの方々の協力を得て動物行動記録計をいろいろ製作することができました。これにより記録計のさらなる小型化や、多様なセンサーの同時搭載が可能となり、例えば動物の3次元の動きや、画像がとれるようになりました。そして長期間にわたる大量のデータが簡単に得られ、デジタル記録計の威力がわかりました。そこで世界中の研究者に声をかけ、「国際バイオロギングシンポジウム」を2003年に開催し、これからはバイオロギング研究を国際的に協力して進めることになりました。
私の個人的課題、すなわち「潜水底部問題」です。このため加速度計をアザラシの顎に着け、その動きを計ることにしました。加速度計は高速でデータを収録するため、生データのままでは生態を考えられるほど長くとれません。そこで、採餌行動を記号化して取り出す、今で言うAIの手法を用いて長期間採餌行動を計測できるカミカミロガーを考案しました。さっそくキタゾウアザラシに装着したところ潜水底部で採餌を繰り返していることが綺麗なデータで示されました。この7ヵ月間の回遊中の採餌行動がすべて計測できる方法も大きな話題となりました。
次は、このアザラシは何百メートルの深い海に繰り返し潜って何を食べているのかが課題です。当然2010年代のビデオはまだ収録時間も短く採餌行動を撮るには適していません。そこで採餌アルゴリズムをビデオに搭載して採餌時のみ短時間収録(1分間)する方法を考案しました。収録時間を1分間にしたのはカミカミロガーからこのアザラシは餌を食べ始めると立て続けに食べることがわかっていたからです。
この結果、アザラシは中深層(200〜1000m)でハダカイワシなどの小型の魚を大量に採餌することが明らかになりました。とくに興味深いのは、このアザラシは溶存酸素が少なくなる深度帯で魚の動きが止まったときに活発に採餌行動をすること、餌の探索にヒゲを使うこと、深海の生物の発光をも頼りに採餌効率を上げていることです。また、このアザラシは潜降していく過程で睡眠していることも明らかになりました。
われわれの研究から潜水生理学的側面からはわからなかった「動物は生き残るために最善の行動的選択をしている」ことが明らかになりました。またキタゾウアザラシの採餌行動から、海洋の中深層の餌場としての重要性も明らかになってきました。数10億トンと推定される、地球上いまだよく理解されていない生物群集のはたす役割の一端を教えてくれました。さらなる研究が期待されます。
(文 ないとう・やすひこ)
「ペンギン遊泳のダイナミックス」

東京大学大気海洋研究所教授 佐藤克文
私がポスドクとして極地研に在籍し始めた1995年のある日、内藤先生が部屋に来て、「加速度ロガーを作るぞ」って言いました。先生曰く、加速度を動物の体の3軸方向で記録して2回積分すれば水中の位置がわかるとのことでした。数ヵ月後に先生が、加速度ロガーのプロトタイプを持ってきました。1軸しか記録できないし、さらに加速度のプラス成分しかとれないことを聞き、私は不思議に思って、「どうやって位置の計算をするんでしょうか」って尋ねたんですが、先生は、「そういう細かいことは君に任せた」と言う。先生はすべてを任せてくれるタイプのボスです(笑)。
私は1996年に加速度ロガーを持ってクロゼ諸島に行き、世界初の加速度データをキングペンギンからとってきました。潜水開始直後はかなり激しくフリッパー(翼)を動かして、体が揺れている様子がデータに現われていました。一方、浮上の途中、まだ深度60mのところで体の振動が止まっていた、つまりフリッパーの動きが停止していたのです。ペンギンは体内の空気によってもたらされる浮力を使っていると考えました。どのくらいの空気を持っていたのかを実データに基づいて推定してみたところ、深い潜水ではたくさん空気を持ち、浅い潜水ではあまり空気を持っていないという傾向が見えてきました。その後アデリーペンギンのデータも合わせて、ペンギンは潜る深さを事前に決めて、それに応じて吸い込む空気量を調節していたという論文を発表できました。陸上で飛ぶ鳥の様子は容易に観察できます。例えば電信柱から地面に舞い降りるカラスが滑空するのは誰でも見られます。ところが観察が難しい水中の鳥は、重力の代わりに浮力を使って"滑空"をしていました。バイオロギングによって、初めてそれがわかったのです。
ここからは空中を飛ぶ鳥の話をします。オオミズナギドリに小型の加速度ロガーを装着したら、結果はすぐ出ました。2005年ごろ、私が山階鳥研の成果報告会で「オオミズナギドリはあまり羽ばたかず滑空を主体に飛んでいました」と、自信満々にこれを発表したところ、コメンテーターの日高敏隆先生に、「それは加速度ロガーがなくてもわかりそうな発見ですね」と言われてしまいました。
これに発奮して、さらに詳しく加速度データを解析し、オオミズナギドリの羽ばたき周波数は、離陸するときは7.5Hz、グライディングの合間に行う羽ばたきは4.2Hzであることがわかりました。その後、私は再び亜南極の島に行って、現生最大のワタリアホウドリを含むミズナギドリ目鳥類5種に同じ装置を着けました。羽ばたき周波数と体重の関係を調べてみたところ、大型の鳥ほど低い周波数で羽ばたき、高周波のほうが低周波の羽ばたき周波数よりも右肩下がりの傾きが大きいことがわかりました。両者は体重41kg、翼開長5mのところで交差します。ということは、例えば仮に体重100kgのミズナギドリ目鳥類がいた場合、飛び続けるために必要な周波数では羽ばたけないということになってしまいます。
この結果にとても困ってしまう動物たちがいます。翼竜です。ケツァルコアトルスやプテラノドンといった巨大翼竜は、海際でミズナギドリ目鳥類のような生活をしていたと考えられていますが、彼らの翼開長は先ほどの推定結果よりも大きかったとされているのです。私は2009年に、現生海鳥から得られた結果から類推すると、巨大翼竜に持続的飛翔は不可能であったとする論文を発表しました。私にとって嬉しいことに、2022年に名古屋大学の後藤佑介さんがケツァルコアトルスの滑空性能から考えて、上昇気流を使っていたとしてもやはり巨大翼竜に持続的な飛翔は無理であったという論文を書いてくれました。彼は私が書いた本、『巨大翼竜は飛べたのか』(平凡社新書)を読んでこの分野に入ってくれました。内藤先生が私にしてくださったのと同じように、私もできるだけ大学院生たちに細かい指示を与えたりしないで、自由にやってくださいという方針で接しているので、内藤イズムは着実に次の世代に伝わっていると思っています。
今回、内藤先生から私に宿題が出ていまして、それは「バイオロギングの有望な研究課題は何か」というものです。現在バイオロギングは特殊な手法から、誰もが使う当たり前の手法に変わりつつあるように感じます。ですから、バイオロギングの進むべき道なんて決められないんですね。ですから、私の答えはちょっと変化球になるのですが、「データのオープン化をしましょう」ということになります。
バイオロギングを立ち上げた人たちが、引退し始めています。その人たちのデータが個人のパソコンにしか残っていないという状況が結構あって、データは間違いなく消滅していきます。そこで、データベースを作りました。バイオロギングのデータだけではなく、いつ・誰が・何を・どこで・どうやって着けたかというメタデータと一緒に保存して、公開するシステムを作ったのです。これに保存してもらえれば、データが永遠に残ります。100年後に、絶滅してしまった鳥が21世紀初頭にどんな飛び方をしていたのかわかるのです。ウェブサイト(https://www.bip-earth.com/ja)に行けば、どなたでもデータを閲覧することができますし、バイオロギングの研究をしている人は誰でも無料でデータをアップして、希望があれば公開、公開したくなければプライベートという選択ができます。ぜひ覗いてみてください。
(文 さとう・かつふみ)
「バイオロギングによる海鳥研究の最前線」

国立極地研究所教授 高橋晃周
私は1996年、北海道の天売島でバイオロギングに初めて出会いました。私がウトウの繁殖生態の調査で天売島に滞在中、極地研の加藤明子さんと山本麻希さんが来られ、当時最新の超小型潜水深度記録計を使ってウトウの潜水行動を調査されていました。得られた潜水深度記録を見せてもらううちに、海での鳥の行動を直接測れる技術はすばらしいなと感じて、バイオロギング研究の道を志すことになりました。当時、バイオロギングは圧力センサーを使って潜水深度を記録できるだけでしたが、今ではGPS、ビデオ、心拍数など、いろいろなセンサーを使って、動物のさまざまな生態・生理情報を記録することができます。今日はバイオロギングを使って明らかになってきた日本周辺の海鳥の渡り行動と、南極のペンギンと環境変化の関係をご紹介します。
鳥がどこにいるかを追跡するバイオロギング装置のひとつにジオロケータがあります。照度を連続的に測定することで、日の出、日の入りの時刻を記録し、そこから鳥がいた緯度・経度をおおまかに推定するという手法です。数グラムと小型なので、足環と一緒に鳥に長期間装着して、記録計を回収するまでの移動軌跡を得ることができます。
ジオロケータの記録から、天売島で繁殖するウトウの成鳥は秋にいったんオホーツク海へ北上し、その後10月ごろから南下して日本海南部で越冬し、また3月ごろに天売島まで戻ってくることがわかりました。一方、日本各地のオオミズナギドリは赤道付近へ渡っていって越冬します。日本海にある新潟県粟島のオオミズナギドリはまっすぐ南に向かうと日本列島にぶつかるので、成鳥は対馬海峡や津軽海峡を抜けてから南に向かいます。では幼鳥はどこを通るのだろうかと、名古屋大学の依田憲さんたちが、巣立ち直後の幼鳥にGPS衛星発信機を装着して渡りのルートを追跡しました。その結果、粟島を巣立った幼鳥は日本列島を横断して太平洋側へ抜けてから南へ向かうという、驚きの事実がわかりました。成鳥は陸地を避けて対馬海峡・津軽海峡を抜けていくのですが、幼鳥は日本列島の少なくとも標高1500mくらいの山の上を飛んでいます。幼鳥は地形に関わらず、巣立ったらまっすぐ南へ行くようプログラムされているのではないかと推測されています。
日本周辺の海域を利用しているのは、日本で繁殖する海鳥だけではありません。ジオロケータを使って、アラスカにあるセントローレンス島のハシブトウミガラスが4000km以上離れた日本海へ渡ってくることがわかりました。逆に赤道よりも南からは、オーストラリアのハシボソミズナギドリやニュージーランドのハイイロミズナギドリが南半球の冬、つまり北半球の夏の間に日本周辺海域に渡ってきます。ほかにもカナダ西岸のウミスズメ、ハワイのアホウドリ類もやはり日本周辺海域に渡ってきます。日本周辺の海は世界各地の海鳥が集まる場所で、この海の保全は、世界の海鳥の保全を考えるうえで重要であることが、バイオロギングによって明らかになったのです。
南極の環境変化とペンギンの関係の研究でもバイオロギングは重要な役割をはたしています。南極は温暖化しているというイメージをお持ちかもしれませんが、実際には南極の中でも地域によって温暖化の傾向は大きく違います。南極から南アメリカ大陸に突き出した南極半島では、50年間で2.74度の速いペースで気温が上昇しています。一方で日本の昭和基地では温暖化の傾向はまだ見られていません。
ペンギンの数の変化はどうでしょうか?温暖化が顕著に進んでいる南極半島では、1970年代から2010年代までにアデリーペンギンの個体数が80%近く減少しています。一方で、昭和基地周辺では、日本の観測隊が1960年代からカウントを続けていますが、個体数は増加傾向にあり、近年は過去60年間で最大の数になっています。
なぜ個体数の変化の傾向に地域差があるのでしょうか?温暖化が進むと、海に張る氷、海氷が減少します。緯度が低くて気温が比較的高い南極半島では海氷に依存したオキアミが減少し、ペンギンの食べ物が少なくなって、個体数が減ったと考えられています。一方、緯度が高く気温が低い昭和基地周辺のペンギンの繁殖率は氷が少ない年に高いという、南極半島と逆の傾向がありました。その理由を探るために、バイオロギングを使って氷がペンギンの行動に与える影響を調べました。昭和基地のペンギンに装着したGPSの記録によると、氷が海を覆っている年にはペンギンは氷上を歩かなくてはならず、移動速度が遅くて狭い範囲しか動けません。しかし、氷がないと、ペンギンは泳げるので、広範囲を短時間で動いて効率よく食べ物を得ることができます。ペンギンの背中に装着したビデオの映像からも、氷がない年に水中で速いスピードでオキアミをとっていることがわかりました。結果的に、氷がない年には、氷が多い年に比べて、親や雛の体重が重く、繁殖率が高くなっていました。南極半島と昭和基地での結果を合わせて考えると、アデリーペンギンと海氷の関係には微妙なバランスがあり、氷が多すぎず、少なすぎず、中程度に存在するときが最も好適な環境であるということが明らかになりました。このように、潜水深度記録計からスタートしたバイオロギングの技術は、いまや野外における動物生態研究の基盤的な調査手法になってきたといえると思います。
(文 たかはし・あきのり)
質疑応答
(質問1)ケツァルコアトルスの大きな翼に機能的なものがないとは考えにくいのではないか。
佐藤 実際は上腕骨から推定されている現在の翼開長の値よりももっと短く、ピンチのときだけ飛ぶ程度だったと考えている。
(質問2)なぜV字型の潜水時間の下がっているところがアザラシの睡眠だとわかったのか。
内藤 ビデオを頭に着けたアザラシが、海底でぶつかって弾んでいて、砂煙が上がっても泳いでないという映像がいくつもあり睡眠だということになった。
(質問3)ペンギンの空気を飲み込む量が違うということは、その深さに魚は多いかどうかを認知できるような機能があるのか。
佐藤 経験や時間経過、前後関係で、どの深さに魚がいるのかを予測しながらふるまっているのではないか。
(質問4)幼鳥のときは日本列島を危険だけど通り過ぎていたのが、大人になって海上のほうが安全だと感じる機能があるのか。
高橋 わからない。1歳から繁殖を始めるまでの数年間は繁殖地に戻ってこないので、調査のしようがない。その間に、徐々に海の上しか飛ばないということを覚えていくのではないか。
(質問5)ペンギンが急浮上、急潜降するときに、減圧症は起こるのか。
佐藤 アザラシは空気を吐き出してから潜り始めるが、これは酸素のほとんどを血の中、もしくは筋肉中に溶かした状態で潜る。ペンギンは空気をたくさん体内に持った状態でディープダイブして急浮上するが、結果的に減圧症にかかっていないのはたしかで、どうやって回避できているのかはまだわからない。
(質問6)バイオロギングができる一番小さな生き物は何か。
高橋 昆虫に着けられるビデオカメラ(0.2g)がある。ロボティクス専門の人が開発して、甲虫のゴミムシダマシに着けた例がある。
<関連ページ>
- *山階芳麿賞について
- *第23回山階芳麿賞報道発表資料
- *第23回山階芳麿賞受賞者
- *講演会プロモーション動画(山階鳥研公式 YouTube)
- *講演会パンフレット(pdfファイル)
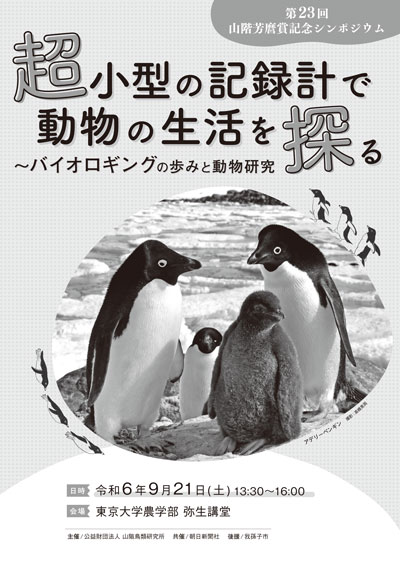
- *ポスター
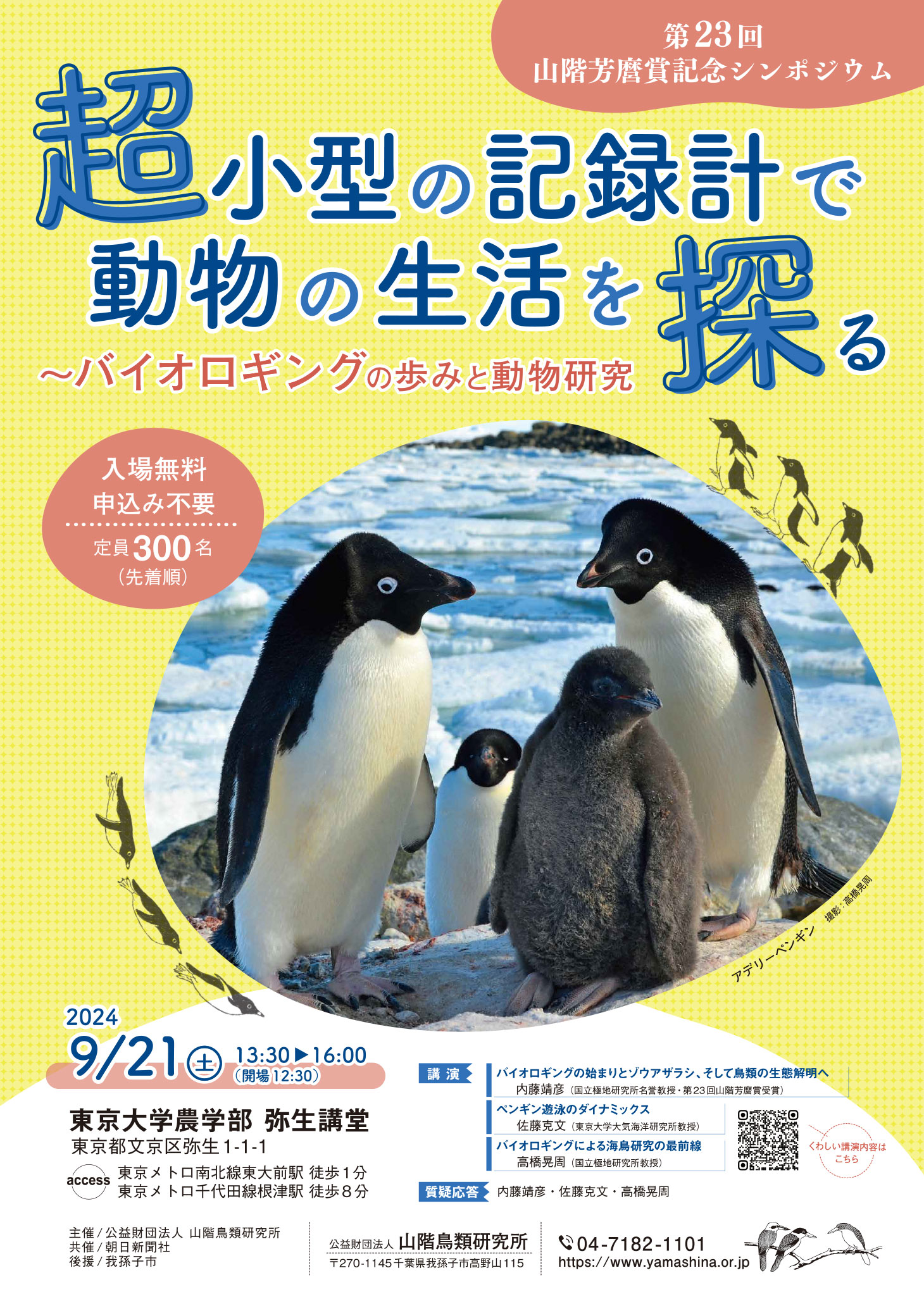
- *チラシ